OSSよろず相談室が
選ばれる理由
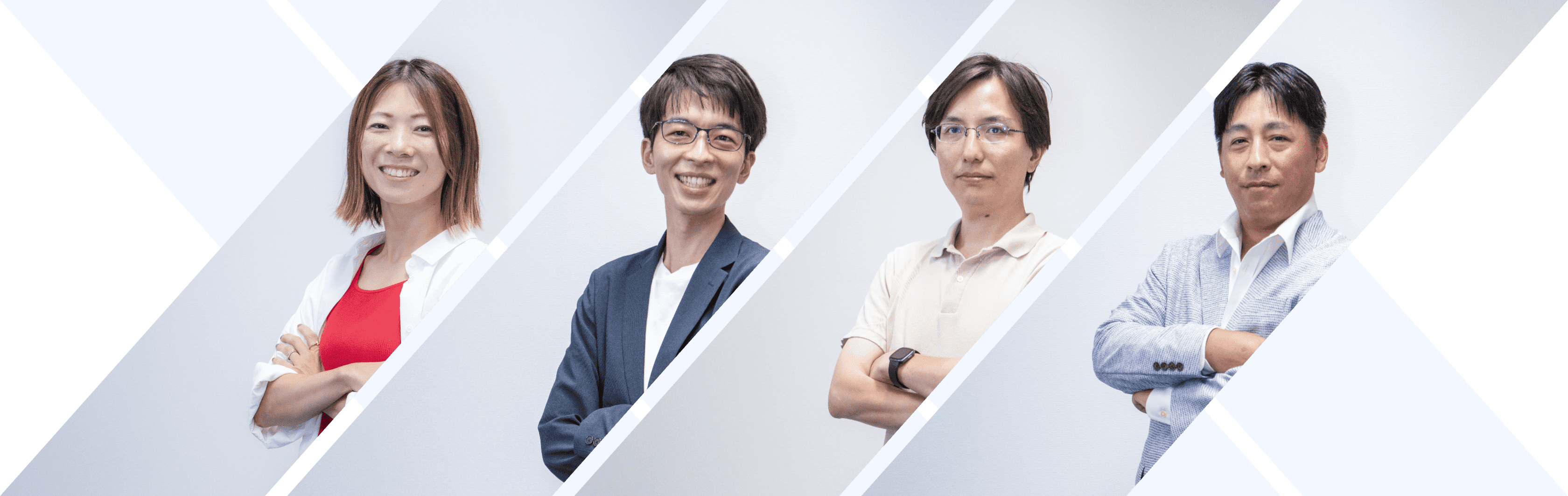

- 貝野 友香
- 調査対応の担当エンジニア
2012年よりOSSサポート業務に従事
問い合わせ対応、外部向けの情報発信 (ブログ、ライブ配信等)を担当している。得意技術はJava。

- 橋本 惇史
- 調査対応の担当エンジニア
2020年よりOSSサポート業務に従事
問い合わせ対応全般、DB サポート、SCANOSS サポートを担当している。前職ではインフラエンジニアとして、WEB、メール、DB サーバなどを運用。得意技術はデータベース、自動化。

- 鎌田 啓佑
- シニアエンジニア
2008年よりOSSサポート業務に従事
問い合わせ対応全般、回答文のレビュー、システム管理を行っている。得意技術はJava、メール、自動化。

- 佐藤 仁
- シニアエンジニア
20年以上OSSサポート業務に従事
対外顧客対応、回答品質管理、セキュリティ全般をリードしている。
目次

- 貝野 友香
- 調査対応の担当エンジニア
2012年よりOSSサポート業務に従事

- 橋本 惇史
- 調査対応の担当エンジニア
2020年よりOSSサポート業務に従事

- 鎌田 啓佑
- シニアエンジニア
2008年よりOSSサポート業務に従事

- 佐藤 仁
- シニアエンジニア
20年以上OSSサポート業務に従事
サイオスOSSよろず相談室について

「サイオスOSSよろず相談室」は、どのようなサービスでしょうか?
- 鎌田
- OSSよろず相談室は、150種類以上のOSSに対応したサポートサービスです。お客様がOSSを使っているうえで、困ったことなどについて質問をいただき、それに回答いたします。
どんな相談が多いですか?
- 鎌田
- 一番多い質問は、うまく動かず、エラーメッセージが出力されたログを確認したがこれはどういう意味か、というものですね。そのほか、こういう動作を実現したいがどう設定すればいいか設定方法や動作仕様といった質問などに対して、トラブルシューティングを行っています。
どのようなお客様が利用されているのでしょうか?
- 鎌田
- 分野は基幹系やWeb系など多種多様ですね。基本的にOSS自体はコミュニティではサポートサービスを提供していないので、企業が使う上でサイオスがサポートの相談を受けるということでご利用いただいています。

どのようなフェーズで導入されるのでしょうか?
- 佐藤
- それもさまざまですね。「これから入札するので5年後」ということもありますし、「すぐに必要」ということもありますが、多いのは「これから運用を開始するタイミング」だと思います。
他社サポートと比べて、どこが違うと感じますか?
- 佐藤
-
一番の特長としては、連絡すると直接すぐにエンジニアが回答してくれる点です。受付窓口が問い合わせを受けて振り分けるのではなく、ご質問にお答えできるエンジニアに直接つなぐため、すぐにコミュニケーションを開始し、問題を即座に解決できます。
そして、回答の質の高さにも自信を持っております。サポート対象となるOSSの豊富さも大きな強みです。なお、この9月にサポート対象OSSを拡充しました。
こうした取り組みにより、20年以上の実績と累計2,000件の契約を獲得しています。
徹底した調査や検証に裏付けられた最適な回答

サポートでの体験から、特に大変だった案件や、印象に残っている案件を教えてください。
- 貝野
- ソフトウェアの動作仕様に関するお問い合わせで、公式ドキュメントや、過去のOSSよろず相談室のサポート事例から情報が得られず、ソースコードを調査して確認することになった案件がありました。このときは、対象OSSの1つのソースファイルの確認だけではわからなかったので、複数ファイルのソースコードを網羅的に調査する必要があり、非常に多くの時間を費やしました。
それは、バグの調査でしょうか?
- 貝野
- いえ。この件の場合は「どうしてこういう動作になるのか」というお客様の疑問でした。そのため、なぜこのように動作しているのか仕様を調査し、説明として提出しました。
なるほど、そういう疑問にも答えてもらえるのですね。
- 貝野
- はい。それほど数は多くありませんが、動作の理由を知りたいというお客様のために、こちらで調べて説明することもしています。
お客様に「ありがとう」と言われた印象的なエピソードも教えてください。
- 橋本
-
これもやはり複雑なご質問を受けたときの話になりますが、調査して解決策を回答してお客様にご納得いただけたときに、「ありがとう」と言っていただくことがあります。
たとえばよくある問い合わせの一つに、「パラメータ〇〇で設定できる上限値はありますか」というものがあります。親切なOSSのなかには文書化していることもありますが、書かれていないことも多いのです。そうしたケースではわれわれがソースコードを調査して回答します。
具体例としては、SQLのIN句(複数の値を条件として指定)について、PostgreSQLではいくつまで値を指定できるかという問い合わせがありました。ドキュメントには記載がなく、ソースコードを調べても上限を規定している部分は見つかりませんでした。検証したところ、リソース状況によって800万件処理できる場合や100万件で処理できなくなる場合もあることが判明し、その検証結果を回答しました。100万件で処理できると検証できればおおよその環境では要件を満たせることや、リソースによって異なることは貴重な情報ということで、お客様には大変感謝されました。

そこまでの調査はお客様が検証するのも難しいですよね。
さて次の質問として、日々のサポートで、特に大切にしていることは何ですか?
- 鎌田
- 私は、お客様が質問されたとき、なぜこのような質問が出たのかという経緯を掘り下げて確認することを心がけています。文字どおりの質問に答えても、追加でまたご質問いただくこともよくあるので、お客様が本当に聞きたいこととのずれを少なくなるようにしています。
- 橋本
- 私は、動作検証することを大切にしています。OSSで指定するパラメータは複雑に絡んでいることあって、たとえば「パラメータAの指定はパラメータBで上書きされる」けど、「パラメータCがあるとそもそも無効化される」といったこともときどき発生します。そうしたことは、机上だけでは勘違いすることもあるので、実際に動作検証をして裏取りすることを心がけています。
- 貝野
- 私は、お客様の質問背景も考慮して回答することを大切にしています。お客様は、問題が発生したため問い合わせされる場合もあれば、将来問題が発生したらどうなるのかを危惧してお問い合わせいただく場合もあります。問題が起きている場合はログや設定の情報が必要となり、状況によって必要な情報は変わります。そのうえで、ご利用のシステム構成などもヒアリングして、最適な回答を案内できるように心がけています。
いま注目しているOSS

オープンソースでは新しいソフトウェアが多数発表されるだけでなく、以前からのオープンソースも機能追加など発展が続いています。そんなOSSをどのように学んでいますか?
- 貝野
-
日頃アンテナを張って情報を仕入れています。たとえば、チャットツール上でサポートのメンバーとやり取りをするなかで、気になる言葉で出てきたら、何だろうと思って調べることがあります。
その調査時間の捻出としては、サイオスでは業務時間の5%を自由活動に充てることができる制度があるので、その時間を利用して、ドキュメントを調べたり、検証したりと、新しい情報に触れるようにしています。
特に初めて知った新しいソフトウェアは、どう動作するかなどよくわからないことがあると思いますが、どうやって調べるのでしょうか。
- 貝野
- 私の場合、最初はドキュメントから概要を把握して、それからドキュメントではイメージがつかめない部分を検証してみるようにしています。
- 鎌田
- やはり、まず動かしてみるというところですかね。動かしてみて、どんな動きするのかいろいろ実験をしてみることが多いかと思います。
そうしたなかで、皆さんが個人的に、いま注目しているOSSはありますか?
- 橋本
-
私は「SCANOSS」に注目しています。これは、ソフトウェアから構成する部品を検出してSBOMを生成するツールです。
昨今は生成AIなどで出力されたソースコードを利用することがあると思いますが、その出所がわからないと、意図せずライセンスに問題のあるソースコードが含まれる可能性もあります。SCANOSSは、そうしたものを検出するツールとして、AI時代において成長するツールではないかと考え、注目しています。
参考リンク
- 佐藤
-
注目しているのは、ローカルで使えるOpenAIの言語モデル「gpt-oss」ですね。やはりAIに関する問い合わせも多く、需要が高まっている実感があります。
参考リンク - gpt-oss が登場 | OpenAI
https://openai.com/ja-JP/index/introducing-gpt-oss/
- gpt-oss が登場 | OpenAI
- 貝野
-
「gpt-oss」は、特にOSSを扱う人が注目しているため、私も注視しています。
もう1つ注目しているのは「Dify」です。AIのツールを、プログラミング知識がなくても作成して利用できるというものです。ITのプロ以外にAIの活用が加速するのではないかと考え、挙げました。
参考リンク - Dify
https://dify.ai/jp
- Dify
- 鎌田
-
私は「Ansible」(構成管理ツール)と「Podman」(コンテナランタイム)です。私は最近、「@IT」でPodmanに関する連載記事も執筆しましたが、以前から自動化やコンテナ技術に関心があるので挙げました。
今後も、自動化やコンテナ技術で新たなOSSが出てきたら、まずは注目していく予定です。
参考リンク - Ansible Automationコンサルティングサービス
https://sios.jp/products/it/container-consulting/ansibleautomation/ - Podman
https://podman.io/ - 次世代コンテナエンジン「Podman」「Podman Desktop」入門(1) - @IT
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/2412/03/news001.html
- Ansible Automationコンサルティングサービス

さきほど9月にサポート対象を拡充したという話がありましたが、どういったOSSでしょうか。
- 鎌田
-
5種類のOSSを拡充しました。これまでサポートされていなかったものの、問い合わせが多い、フレームワークやその他の広く使われているツールを追加しました。
Dify Backend as a Service (BaaS) と Large Language Model Operations(LLMOps) の考え方を融合したオープンソースの AI アプリ開発プラットフォーム NetworkManager 多くの Linux ディストリビューションにおいて標準で採用されているネットワーク設定ソフトウェア Systemd 一般的な Linux ディストリビューションに標準で採用されているサービスマネージャ Spring Boot Spring ベースのアプリケーションを素早く、簡単に開発することができるフレームワーク Spring Framework 依存性注入 (Dependency injection) や、アスペクト志向プログラミング (Aspect oriented programming) といった特徴を持つ Java アプリケーション開発フレームワーク
サポート対象の決定は、サポートできる目処がついたかどうかで決まるのでしょうか?
- 鎌田
- そうですね。どのように使うのか、サポート対象に加えた場合にどのような知識や情報が必要なのかといったことを全部洗い出します。そして、当社のメンバーでサポートが可能か検討したのち、内部の勉強会なども実施しつつ、サポート対象に組み込むという流れです。
質の高い回答を実現するチーム体制

仕事を始めてみて、担当する前と担当後で感じたギャップはありましたか?
- 橋本
- ギャップとしては、既知のバグに合致する事例が、思いのほか少ないという点があります。お客様から「動作がおかしいのでこれはバグですか」という問い合わせをいただいても、実際にはパラメータ設定のミスだったり、CPUやメモリ、ディスクI/Oなどのサーバーリソースが不足しているのが原因だったりします。そのため、既知のバグに合致していることが確認できたときは、むしろ驚くこともあります。
新人メンバーが安心して取り組めるように、体制面で配慮していることはありますか?
- 佐藤
- リーダーとして上に立つ私としては、OSSよろず相談室は20年以上続けてきて、新卒者が配属されても適切に育成できる体制を重要だと認識し、実際に確立できていると思います。そのうえで、興味ある分野を聞いて、どのOSSを担当してもらうという基準は作っているので、初めてサポートに入ったとしても対応に困るようなギャップは少ないと考えています。
それに関連して、さきほど回答の品質への自信を伺いましたが、そのポイントを教えてください。
- 佐藤
- 回答レビューに携わる者として胸を張って言えるのは、お客様に一生懸命対応して経験を積んだ人を揃えているので、問題に先回りができるという点です。そのため、質問に対して、適切な回答を適切なレベルで返すことで、お客様の担当者の方も注意すべきこと認識して、一体となって問題解決に取り込むことができているのではないかなと思っています。何よりも重要なのは、質問内容に対して適切な証跡を示した回答を提供できる点です。それが可能だからこそ、自信を持ってサービスをお客様にお勧めできるのです。
問題解決において、チームだからこそ解決できた事例はありますか?
- 鎌田
- 以前受けた問い合わせで、データベースとOSにわたって調査が必要な問い合わせがありました。そこで、データベースが得意なメンバーと、Linuxカーネルが得意なメンバーで分担して調査して、解決に導いたことがあります。そのほか、ドキュメントとソースコードなど、複数人がそれぞれの得意な分野を調査することで、回答の品質を上げることにも役立っていると思います。

チームの雰囲気はいかがでしょうか。
- 橋本
- いいチーム感でまとまっていると思います。上からの指示に従うだけではなくて、確かな論拠を持って反論するのであれば、肩書など関係なくフラットに会話ができるのが、プロフェッショナルなチームとして良い点だと思います。
- 佐藤
- 私たちは徹底的に議論して、チームみんなで納得したうえで一致団結しながら取り組むことができていると思っています。
最後に、OSSよろず相談室を検討されるお客様へのメッセージをお願いします。
- 佐藤
-
冒頭でもお話したように、OSSよろず相談室は、20年以上の歴史があり、延べ2000件の契約があります。それが技術力の高さを示していると自負していますし、お客様に選ばれる信頼性につながっていると確信しています。
もともとこのサービスは、お客様の障害対応者における強力なツールとして当社のOSSサポートで支援しようということで始め、お客様とともに疑問と難問に立ち向かうことに多くの時間を費やしてきました。ご関心をお持ちの企業のご担当者の方には、さまざまな側面でご相談いただき、ぜひサイオスOSSよろず相談室にご興味を持っていただければと思います。
OSSサポートでの長年の実績と技術力に基づいた信頼ということですね。ありがとうございました。
